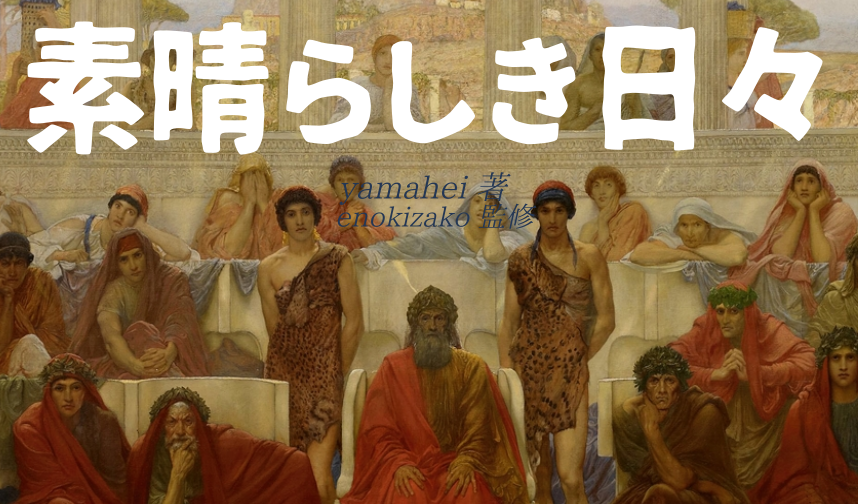マネージメント職の9割方は割に合わない

プログラマーから叩きあげて成長していくと、チームを持つようになったり大きなプロジェクトを任されるようになったりするでしょう。 やり甲斐を感じる方もいると思いますが、冷静に振り返ってみると割に合わないと感じることも多いです。
残りの1割
いわゆる業界最大手クラスのスーパーホワイト企業には本記事は当てはまらないようです。 つまりは上に顧客しかいない、世に問う立場の会社はマネージメントの重要性を理解して人材を育成しているように思います。 これは規模が小さくても広く受け入れられているWebサービスを運営している会社でも同じように感じます。
最大手の地方子会社クラスになってくるともう怪しくて、気持ちはあっても現実に引きずられているような印象を受けます。
マネージメントへの無理解
「段取り八分、仕事二分」という言葉があります。 特にシステム開発は漠然とした需要に対する提案を行うことが多いためか、方向性を定めた上で走り出さないとコケます。
プロジェクトをスムーズに進めるために段取りは重要な期間ですし、これはマネージメントの範囲です。 組織の上層部にはなぜか「人海戦術が始まっていない=プロジェクトが立ち上がっていない」と感じる人が多いようで、このタイミングでのコスト増は頑として認められないことが多いです。
準備にかかるコストが承認されないのにプロジェクトがコケたらマネージメントに責任があるってのはどうにも納得がいきません。
マネージメント教育の不足
教育と実践は人材育成の両輪ですが、新卒教育以降コストをかけて社員教育できていない会社は多いです。 一応資格手当があり、自分で頑張ってね~というスタンスが多いです。 親会社に縛られていない独立系なんかほとんどそうなんじゃないかと思います。
知識不足で実戦投入されて失敗、それでも何とか戦えるようになってきた頃に転職。 経験則でマネジメントっぽいことができてるだけなので言語化できず、誰にも継承できずにいなくなるので会社にノウハウは蓄積されない。
コストをかけて教育しないことで、人材流出による損失のほうが大きくなってしまう悪循環はそこらじゅうで目にします。
報酬面
新卒採用からの生え抜き社員の昇給幅の大きさはそのまま会社の底力を表しています。 一部上場企業などはドンドン昇給しますが、今回のテーマである9割方に当てはまる会社はまあ上がりません。
だからみんな転職して給料アップを目指します。 先の教育不足と相まってマネージメント経験を積んで転職(給与アップ)することを目標にしているエンジニアは多いです。
悪循環を断ち切る
最大手の地方子会社クラスといえば悪くない会社ですが、それでも本記事の9割に該当するのはなぜなんでしょう? 私が思うに、「上が顧客ではない=下請け体質」が影響しているのかなと思います。
下請けの報酬には相場があるため利益率も頭打ちになりがちで、社員の給与も相場を超えて上げることはできません。 これが教育にコストをかけられない原因につながっていくのではないかと推測しています。 つまりカネがないと悪循環は断ち切れない。
だからみんな利益率の高い自社製品を目指すんですね。 ただイマドキは個人でWebサービス作るのも難しくないので、個人で当てる→法人化してホワイト企業を作るという流れの方がありそうな話です。
- 謝辞
- 画像は Wikimedia Commons 様より使わせていただきました。